2020年度GTR Research Awardインタビュー
GTRでは、学生の融合研究の成果や異分野に挑戦する姿勢などを評価し、GTR Research Awardとして顕彰しています。
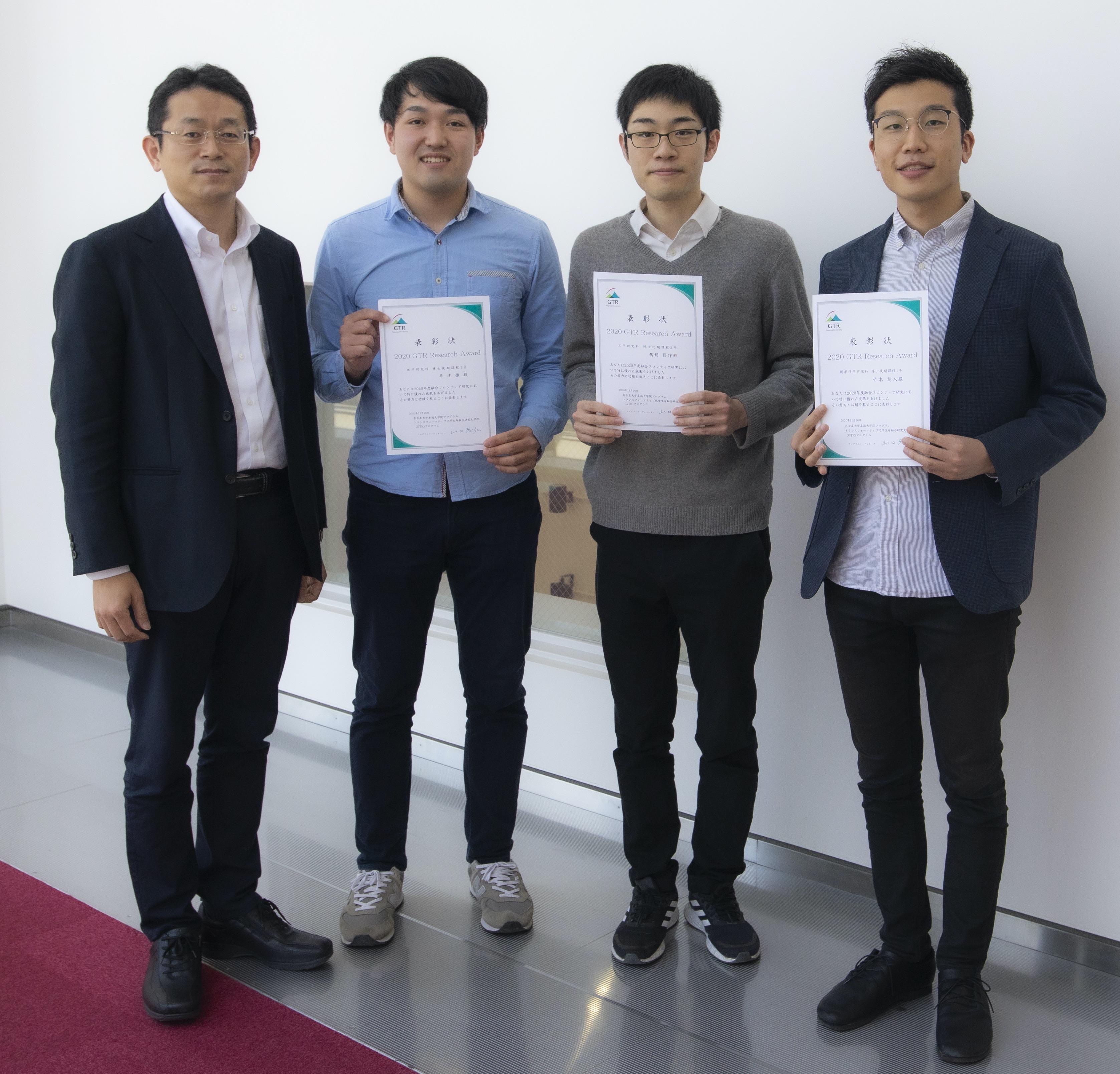
2020年度のGTR Research Awardは以下の3名に贈られました。
今年度の受賞者の3人に、取り組んでいる融合研究の内容や、研究に対する思いなどをインタビューしました。
2020年度GTR Research Award 受賞者インタビュー
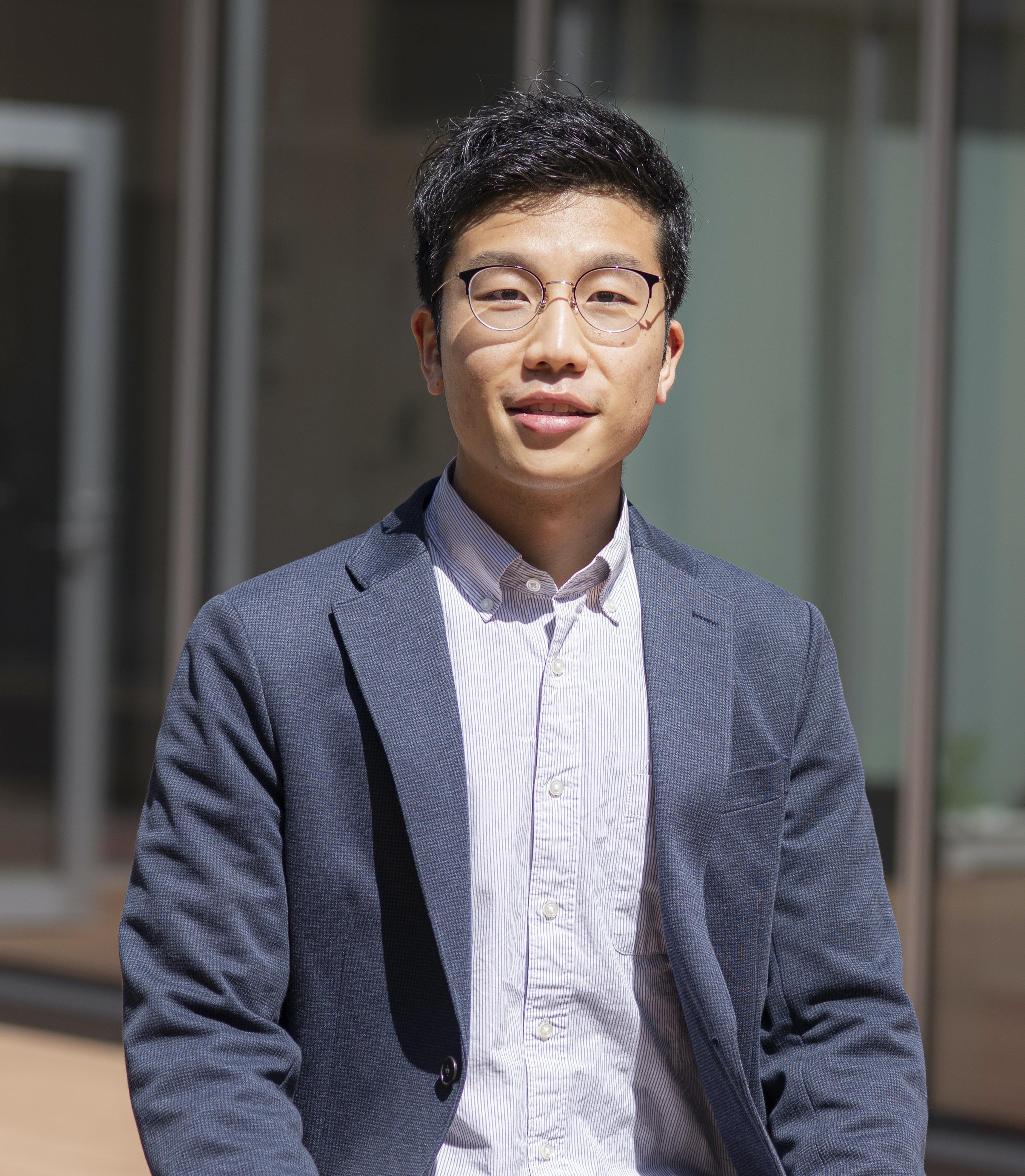
創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 博士後期課程1年
「現場で使える技術」にこだわる
創薬科学研究科の細胞分子情報学分野に所属し、細胞の画像情報を使って、細胞の形から細胞の品質を予測する研究をしている。遺伝子情報やタンパク質の発現の様子を調べる従来の方法は、極めて的確に細胞品質評価が行えるが、操作が煩雑であり、破壊的・非効率・高コストといった課題があった。
再生医療や創薬などの目的で細胞を大量に培養する現場では、増殖率の良さなど「細胞の品質」を効率よく見分けるニーズがあり、画像情報から細胞の品質を予測できれば、従来の課題を解決することができ、細胞製造の現場などで役立つ。
「例えば、細胞を染めれば輪郭がはっきりして画像から形の情報を取り出しやすくなりますが、そうするとその細胞は製品としては使えなくなってしまう。私たちの研究室では、あくまでも"製造工程に組み込む"という目的を重視して予測モデルを開発しています」
生命科学と情報科学の融合領域
自身の研究テーマとしては、様々な環境で取得されたデータに対応できるロバスト(頑健)さを備えた予測モデルの開発を目指している。撮影された細胞の画像は実験者や機械によってばらつきがあり、細胞の種類によっても得られる画像は全く異なる。そうした画像の質などが変化しても細胞の品質を予測できる、汎用性の高い解析手法の開発が目標だ。
「細胞は、常に動いて状態が変わっていく。ロバストな解析を実現するには、解析に不要なノイズとなる情報を判断し、除去していく必要がありますが、細胞の動きの生物学的な意味を理解していないと、必要なデータと必要でないデータを判断できません。生物と情報、双方の領域の理解が必要な研究テーマです」

課題設定と優先度を明確に
効率的な細胞品質評価技術は、細胞製造企業に限らず、細胞培養用プレート・培地の開発を行う企業など様々な分野で必要とされている。こうした企業には複数の条件・培養用基材を効率的に評価したいという共通のニーズがあることから、細胞画像による品質評価が求められ、所属する研究室ではこうした企業との研究プロジェクトも多い。自身も、研究で得た解析技術を応用できるよう、様々な企業との研究プロジェクトに取り組んでいる。
企業が抱える課題を解決する研究プロジェクトと、自身の専門研究とは、スタンスを切り替えて臨んでいるという。「企業との研究プロジェクトでは、できるだけシンプルな解析プロセスで、求められているゴールにたどり着けるよう心がけています。専門研究として深堀りしているような解析の手法を組み込んでしまうと、一見その方がよい結果が得られると思っても、相手が求めるものとは優先度が違っていた、といったことが起きます。課題解決のために必要なことはどれかを見極め、無駄な解析はしない。最初に、ゴールまでの最短距離を見つけ出すことが大切だと思っています」
企業との研究プロジェクトを通じて、バックグラウンドの異なる相手と一緒に仕事を進める上で重要な点も学んだ。「最終的な到達点や、ゴールにたどり着くまでの過程で難しい箇所、そこをクリアするために必要な時間など、できるだけ早く、相手と認識を共有するように心がけています」
自分自身のロバスト性を高める
高専時代は高分子化学、学部時代は極限環境で生きる古細菌の研究と、現在とは全く異なる分野を専攻していた。研究が直接社会の役に立つことに惹かれ、大学院から現在の研究室に飛び込んだ。ゼロからのスタートでも迷いはなく、「新しいことを学びたい」という冒険心の方が強かったという。
様々な環境に身を置くことで、「それまで当たり前だと思っていたことが、そうではないと実感できる」と話す。
GTRでの活動を通じた異分野との交流も、「自分の研究とコラボできるかという視点だけではなく、純粋に色々な分野を知ることができるのが楽しい」という。
色々な人、多様な考え方に触れることで、世界を客観的な目で見ることが鍛えられる。そうした経験が、「自分自身のロバスト性」につながると考えている。
(2020年12月オンラインにてインタビュー)
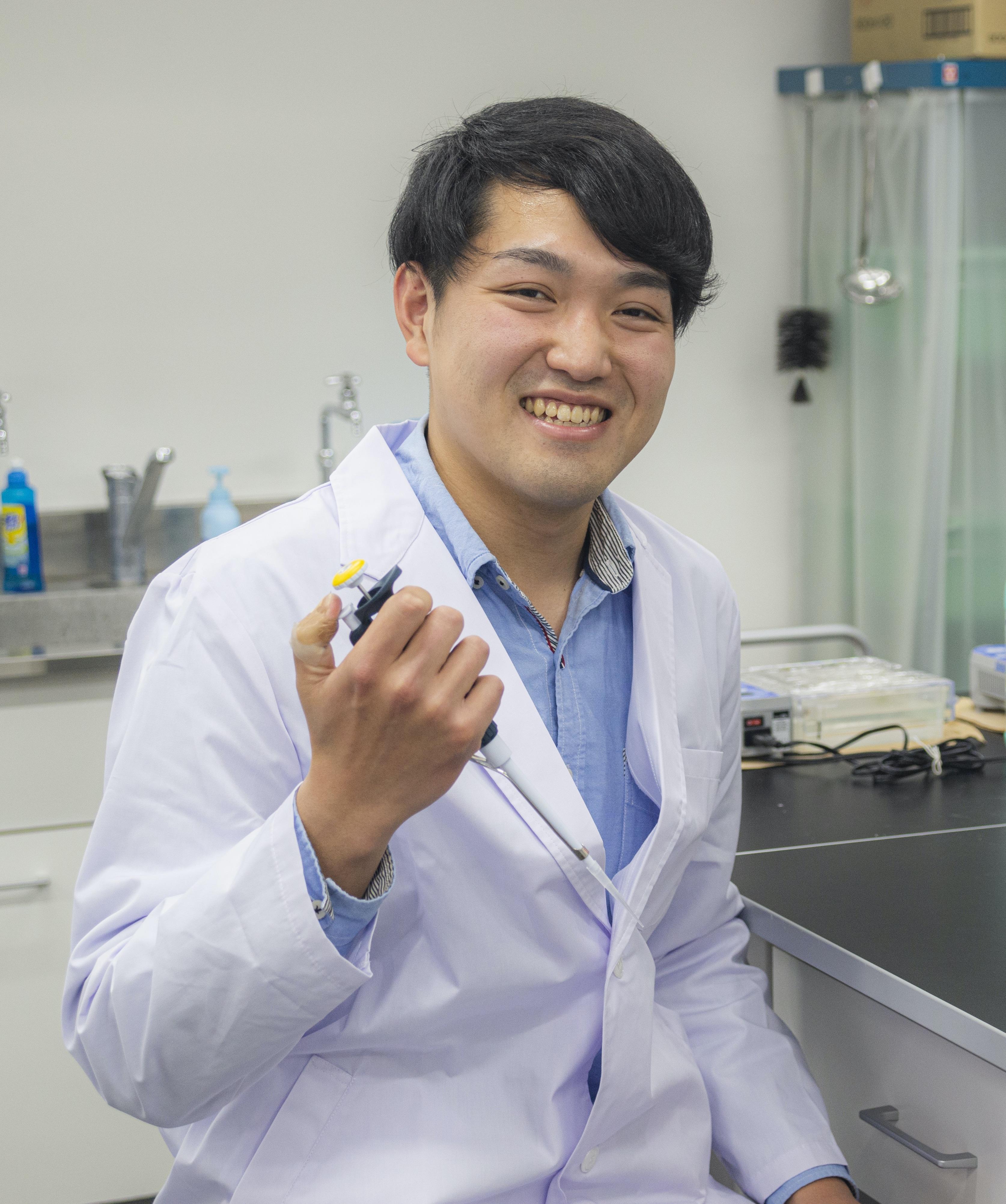
理学研究科 生命理学専攻 博士後期課程1年
子どもの頃から続けている、サッカーを通して学んだこと
小学生の頃から、ずっとサッカーを続けてきたそうだ。大学院に在籍する今も、社会人チームでプレーしている。
サッカーでのポジションはゴールキーパー。「勝敗を左右する重要なポジションで、精神的なタフさが求められます」
「自分が最善のプレーを尽くした時、それが他の人の笑顔になり、自分も嬉しい」。そんな、自分の貢献が他の人を幸せにする喜びを、サッカーを通して経験してきた。「自分が力を発揮することで、他の人や社会に貢献できるようになりたい」という行動理念は、研究においても同じだと話す。
研究もチームプレー
大学院では、ケミカルバイオロジーのアプローチで、植物の研究を行っている。ケミカルバイオロジーの手法は、まず、解明したい生理現象に変化を与える化合物を探し出す。そして、その化合物が作用するタンパク質を見つけることを通じて、目的の生理現象に関わるタンパク質を特定し、生命現象の理解を目指す。化学と生物学の融合分野だ。
研究という営みは個人プレーの側面が強いと思っていたが、大学院進学後に異分野の研究者との融合研究に取り組むようになり、チーム競技のような達成感と面白さがあると感じるようになったそうだ。「各々が自分の軸を持って役割を果たしつつ、チームに還元する。それぞれの分野のプロの視点や経験、知識がつながることで、新しいものがうまれる。そんなチームプレーと似た部分のある融合研究が、自分には性に合っていると感じています」

ピンチからの転換
GTRの融合研究では、植物の気孔の開閉が、どんな仕組みで制御されているのかを探っている。
現在の融合研究のテーマに至るきっかけは、2019年、修士課程2年の時にさかのぼる。研究室のセミナーで、自身が見つけた化合物について報告した際、見つけた化合物と「カリキン」という化合物が似ている可能性があることを、土屋雄一朗・特任准教授が示唆してくれた。「その時はメモに留めておくぐらいで、特段注目はしていなかったのですが、修士論文を書いている時に、過去のメモを見返していて、土屋先生のコメントを思い出しました」
カリキンは植物が燃えた煙に含まれ、山火事の後に植物の発芽を促す作用を持つことが知られている。また、カリキンは、植物が乾燥に耐える性質にも関わっていることが示唆されていたが、実際にカリキンが植物の気孔を閉じさせる作用があるかは明らかにされていなかった。カリキンが気孔の開閉にも関わっていることを実験で確かめ、カリキンが気孔の開口を阻害するメカニズムを明らかにするための手がかりをつかんだことが、自身の研究成果だ。
現在は、カリキンが種子の発芽を制御する仕組みについて研究する、名城大学の藤茂雄・助教と融合研究を行っている。
当初は、京都大学のグループと別のテーマで融合研究を計画していた。しかし、コロナ禍で思うように研究を進められなくなった。「緊急事態宣言や、大学に登校できないという状態が続いて、"まずい、研究できない"、と危機感に襲われました」。サッカーの試合に例えるなら、カウンター攻撃を受けて失点し呆然、という感じだったそうだ。そんなピンチを打開してくれたのが、修士論文の仕上げに必死だったさなかに着手した、カリキンに関連するテーマだった。「自分では形勢を逆転する"カード"とは気づいていなかった。先生方や色々な方のご協力のおかげです」
一歩一歩、目標に向かって地道にステップを積み重ねる
修士課程では思うような研究成果を出せず、「修士課程のリベンジの思いもあって博士課程に進んだ」という。博士課程に進学した当初は悔しくてやっていた研究だったが、今は成果を実感できるようになり、研究が楽しくなってきているそうだ。厳しい時間帯を耐えた後、ようやくゲームの流れが変わってきた。「やっと、"自分の研究"として進められていると実感できるようになった」と話す。
今回つかんだ手がかりをさらに進展させ、より詳細なメカニズムの解明につなげたい。
「スポーツでは、日々の基礎練習が重要ですが、地味で苦しいものが多いです。研究も同様で、成果が形になるまでには、多くの地道なステップを踏む必要があります。一歩一歩、目標に向かってステップを進めていけるところは、自分の強みだと思っています」
(2020年12月オンラインにてインタビュー)
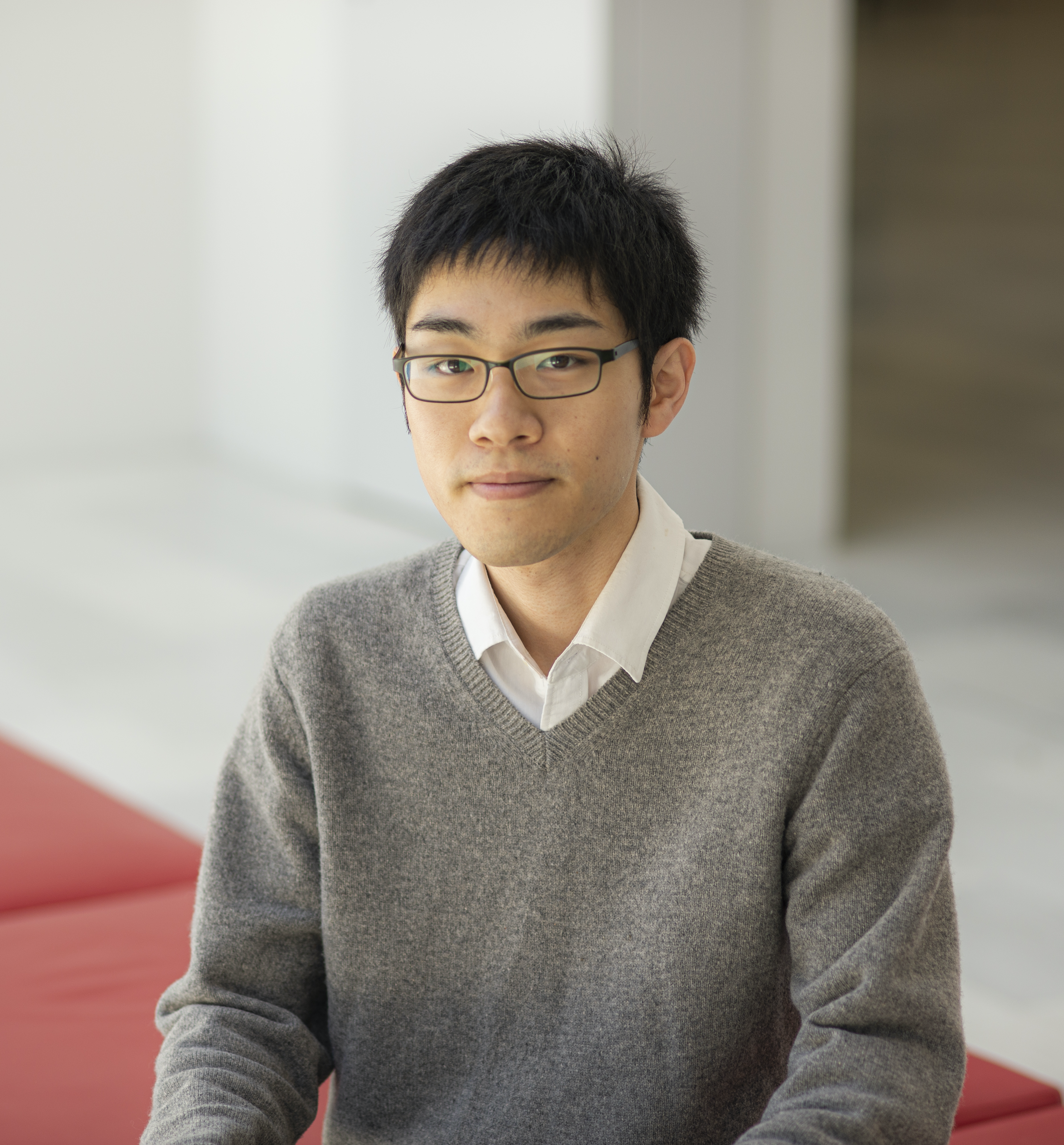
工学研究科 有機・高分子化学専攻 博士後期課程2年
「化学」への思いの原点
高校3年生の文化祭で、仲間と一緒に大砲を作成した。燃焼剤からこだわり、化学反応で生じる熱を利用して気体を膨張させ、弾を打ち出す大砲を考えた。10人ほどのメンバーで分担し、どのような化学反応を行う燃焼剤が良いか、必要な発熱量はどのくらいか、どんな材料ならば高温に耐えられるか、着火システムはどうするか、各々の知恵を結集してつくり上げた。これがきっかけで、「化学反応」を自分の手で「目に見えるモノ」として応用することができる化学の魅力にはまったという。
「使える化学」を志し、大学は工学部を選んだ。
人とディスカッションすることの重要性
現在の名古屋大学の研究室に移ったのは大学院から。
学部時代は他の大学のシラバスまで調べて自身の大学のカリキュラムで足りない科目を洗い出し、自宅に籠もってひたすら化学の勉強をしていたそうだ。
しかし4年生で配属された研究室で、指導教官からディスカッションの重要性を叩きこまれた。「研究は自分一人でやれることはほとんどなく、新しいアイデアは人とタッグを組んでコラボレーションすることで生まれていく。自分のアイデアと相手の考えがミックスされて新しいものが生まれるために、議論することの大切さを徹底して教えられました」
指導教官から「より高いレベルで、多くの仲間と切磋琢磨できる環境で化学を楽しみなさい」と勧められ、大学院から名古屋大学に移った。「同じ化学の世界でのディスカッションという点だけではなく、例えば生物のような別の世界を知ることができたという所も、総合大学に移って良かったと感じている点です」
融合研究を通じて、自身の研究課題を乗り越える
現在は反芳香族分子「ノルコロール」の研究を行っている。
ベンゼン、ナフタレンなどの芳香族分子は身の周りに存在することからも想像できるように一般的に安定だ。一方、反芳香族分子は特殊な電子構造からとても不安定で、身の周りには存在しない。ノルコロールは、反芳香族化合物の不安定さを克服した化合物で、壊れないために周りを置換基の「バリアー」で覆っている。しかしこのバリアーは、反芳香族の持つ特性である電子の受け渡しを邪魔してしまうというジレンマがあった。
自身がこれまでに取り組んできたテーマは「壊れないぎりぎり最小のバリアー」を見つけること。そして、壊れないぎりぎりの「ほぼすっぴん」状態のノルコロールをつくることは達成できた。しかし、ほぼすっぴんのシンプルな構造は溶媒に溶けず、加工したり実際の電子構造を確認したりすることができないといった課題を抱えていた。
GTRの融合研究ではこの課題を乗り越えるため、ほぼすっぴんのノルコロールの分子を、溶液内できれいに並べることに取り組んだ。
「GTRのイベントでのポスター発表をきっかけに、コラボレーションの打診をいただいた時は、正直、難しいんじゃないかと思いました」。融合研究先の研究室が持つ「きれいに分子を並べる技術」を使うためには、まずは自身のつくっているノルコロールの分子に新たな置換基をつける必要があった。「最初聞いた時、この置換基をつけるだけでも、絶対に時間がかかるぞと思いました。でも、もしこの融合研究が出来たら、新しい構造体に生まれ変わることができる、新しいフィールドに突き進めると思いました」
きれいに並べるために必要な前段の化合物を合成するのに、2年近くかかった。
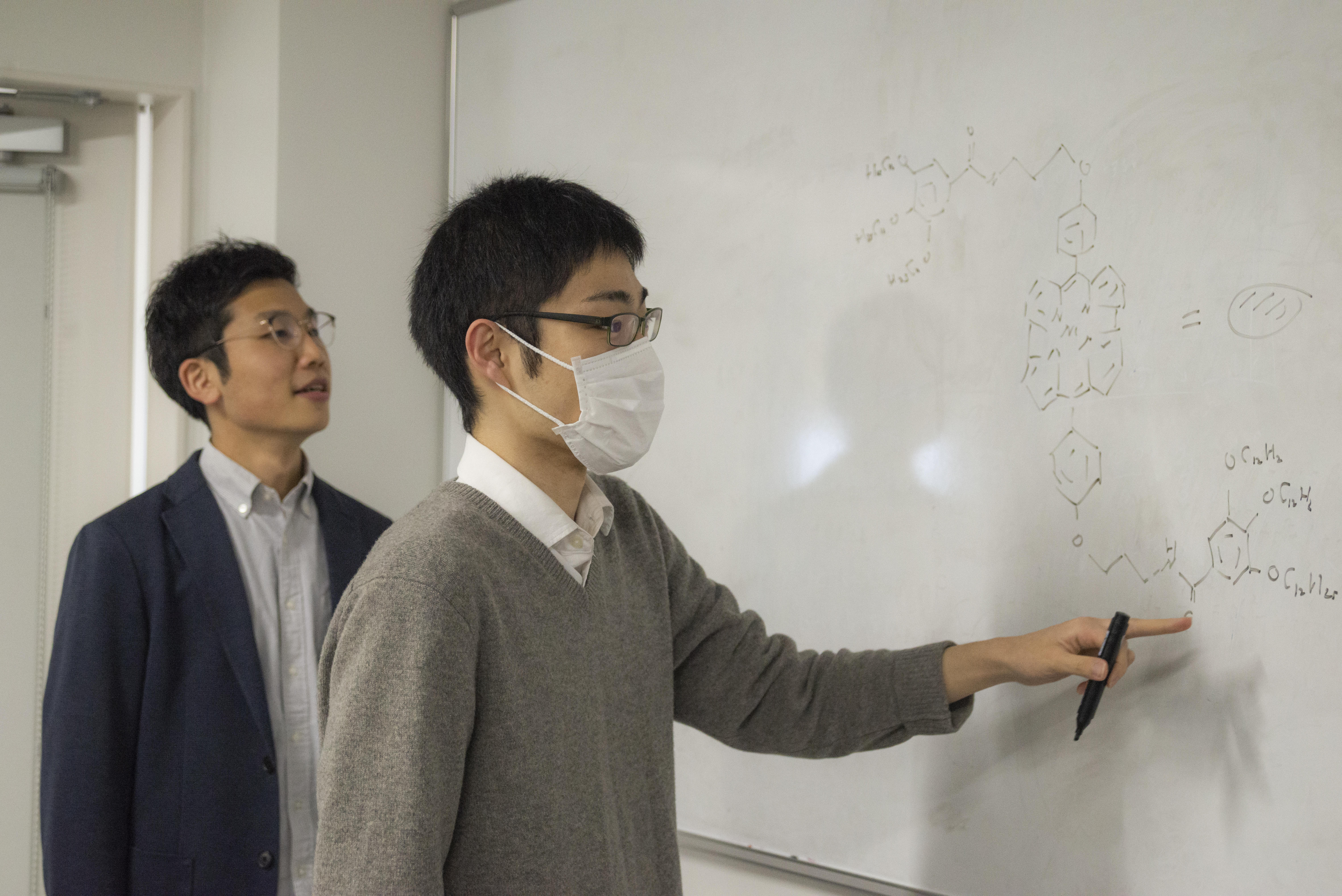
より「高い山」を目指して
現在の到達点をたずねると、「60点か70点くらい」だという。「もともと目指していた反芳香族分子を上手くたくさん並べるということ自体は達成できました。でも、やればやるほど、クリアしたい課題が見えてきてしまって。まだまだやりたいことが沢山あります」
融合研究を通じて課題を一つ一つクリアしていく過程を、GTRのロゴに重ねる。「GTRのロゴは、微妙に高さが違う二つの分野の山が重なって、新しい山を乗り越えている。超えられる山を積み重ねていけば、山をどんどん高くしていけると思っています。もし、今回の融合研究でできた新しい山を、さらに別の分野と一緒に超えられるような新たな出会いがあったら、また別の山にもできるかもしれない。そうなったら面白い」
次の10年で目指すもの
大学に入学した時、10年後に何を達成していたいかを考え「化学をマスターすること」を到達点に決めた。「"知恵をつくる"という所まで行って初めて、何かをマスターできたと言えると思っています。学部の4年間は先人の知恵の蓄積を学び、修士の2年間で知恵をつくるための作業を学び、実際に知恵を形にするのが、博士後期課程だと思っています」。
博士課程修了後は、企業の研究者として、化学の成果を製品として社会に提供できたらと考えている。「次の10年は製品化という形で、自分が目指す "使える化学"を社会で実践したい」
(2020年12月オンラインにてインタビュー)
