2024年度GTR Research Awardインタビュー
GTR Research Awardは、融合研究の成果や異分野に挑戦する姿勢など、学生の研究への取り組みを総合して評価し、その年を代表するGTR生を顕彰する制度です。2024年度は6名にGTR Research Awardが贈られました。
今年度の受賞者に、異分野融合の苦労や魅力、研究に対する姿勢などを聞きました。
2024年度GTR Research Award 受賞者インタビュー

理学研究科 理学専攻(物質・生命化学領域) 博士後期課程1年
強いレーザー光で気体分子を解離させる
物質に強い光を当てると、分子が特徴的なふるまいをする。非常に強力な光であるレーザーを気体に照射し、分子がどのように分解されるかを研究している。将来的には、強いレーザー光を使って化学反応を制御する技術につながると期待されている分野だ。
これまでに、どのようなレーザー光を当てるかによって分子の分かれ方が変化することが確認されているが、そのメカニズムは十分に解明されていない。その背後にある法則を探ろうとしている。
扱っているのは、気体分子の二酸化窒素(NO2)だ。NO2の分子に、山と谷の形が違う非対称なパルス形状のレーザー光を当てると、NO2の分子の中にある酸素と窒素の二つの結合のうち、片方だけを選んで切ることができる。さらに、NO2を高いエネルギー状態にしてからレーザーパルスを当てると、切断のされ方が変わることを見つけた。これは意外な結果だったそうだ。
「予想外すぎて結果に戸惑いました。これをどう説明して論文にまとめようかという不安と、面白い結果を見つけた嬉しい気持ちとが半々でした」
異なる先行研究から説明を組み合わせ、従来の議論に一石を投じる新たな現象として成果をまとめた。
実験を通じて化学反応を解き明かす
理学研究科の光物理化学研究室に所属。化学反応式では、A+B→Cのように反応が矢印であっさり表記されるが、その背景にあるメカニズムをもっと詳しく知りたいと考え、現在の研究室を選んだそうだ。理論研究ではなく、実験を通じて得られる生の情報から化学反応を解き明かすことに魅力を感じている。
「例えば、化学反応には電子の動きが関係していますが、レーザー技術を使うことで電子を分布図として可視化できます。単なる矢印で表されている化学反応の過程に何が起きているのか、そこを知ることに面白さを感じています」
実験はうまくいかないことがたくさん起きる。しかし、そんな時でもあまり焦らず、不安にならないことが大事だと考えている。常に冷静さを保ち続けられるのが強みだと自己分析している。

融合研究のパートナー探しに苦戦
当初、GTR内で融合研究の相手を探そうとしたが、なかなか相手が見つからなかったという。
「液体や固体を扱う化学分野の方はGTRにたくさんいらっしゃるのですが、私たちの研究室の技術で対象にできるのは気体分子なので、そこがネックでした」
GTR内で融合研究相手を探すのは難しかったが、GTRのイベントで異分野の研究者と話をするのは楽しかったそうだ。GTRで融合研究に積極的な雰囲気に触れるうち、「自分も融合研究をしたい」と思うようになったという。
「GTRに入ったことで、融合研究の良さを知ることができました。自分の研究を発展させるために必要な相手を、自分で動いて探そうという積極性を得られたことがGTRでの一番の収穫かもしれません」
現在進めている融合研究のパートナーは他大学の学生で、学会のポスター発表で偶然出会ったそうだ。
分子の中の原子同士の距離(結合長)の変化によって分子全体のエネルギーがどう変化するのかを示した「ポテンシャルエネルギー曲線」と呼ばれるグラフを探していたが、先行研究には自身の研究に合うものが見つからなかった。
「自分でつくろうと思ったのですが、実験が専門で理論計算の知識はあまりなく、苦戦していたところ、学会でポテンシャル曲線をつくって発表している方を見つけました」
話しているうちに仲良くなり、つくり方を教えてほしいと頼んだ。その後やり取りを続けるうち、融合研究につながった。
留学を通して研究者としての視野を広げたい
GTRを履修しようと思った理由の一つは、博士号取得までの充実した支援が得られることだったそうだ。GTRの支援を受けて、カナダへの留学も決まっている。
「もともと留学そのものへの憧れがありました。現地の人と交流し、文化の違いなども楽しみたいと思っています」
留学先は、自分の研究分野の先駆的な研究室。特殊な装置の使い方を学んだり、電子の動きを可視化したりする研究を深めるだけでなく、研究生活の違いにも関心があると話す。
「海外では休日をしっかり取りながら成果を出している。どううまく回しているのだろうと興味があります。長く研究を続けるための秘訣を知りたいと思っています」
アカデミアで基礎研究を続けるつもりだったが、最近は企業の人の話を聞く機会も増え、「社会に役立つ、社会のことを考えて働くのも素晴らしい」と感じるようになり、企業でのキャリアにも関心を持ち始めた。留学でさらに視野を広げ、将来の選択肢を考えたいと話す。
(2024年11月インタビュー)

理学研究科 理学専攻(生命理学領域) 博士後期課程1年
ハエを使って脳における音の情報処理を探る
理学研究科の脳回路構造学研究室に所属。動物における音声を使ったコミュニケーションがどのように成立しているのかを研究している。
実験に使っているのは研究のモデル生物として広く利用されているキイロショウジョウバエ。ショウジョウバエは脳が小さく構造がシンプルで、モデル生物であることから変異体の作成が容易といったメリットがある。
ショウジョウバエのメスは、オスが羽を震わせて発する求愛歌を聞いて、交尾を受け入れるかどうか意思決定している。聴覚によるコミュニケーションが行われているのだ。
「求愛歌を聞いたメスの聴覚ニューロンの細胞レベルの応答や、行動への影響を調べることで、聴覚によるコミュニケーションの仕組みを研究しています」
聴覚ニューロンの応答を数理モデルで表す
特に関心を持っているのが、動物の状態によって音の情報処理が変わる現象だ。
GTRの融合研究として、数理モデルを手がける研究室の協力を得て、神経細胞の応答をモデル化することで、実験で検出できる信号をより詳細に解析し、細胞活動の微細な変化を捉えられるようにした。
「相手方の研究室を初めて訪問して研究を説明した際、先方は教授を含む3人に対し、自分はひとりでプレゼンをしました。ひとつの実験でデータがどれぐらい取れるのか、そのデータを取ることでそもそも何を見ているのかなど、コンピュータを使った数理モデルの研究をしている方々に、生き物を使った実験から取れるデータの意味を理解していただくことが必要でした。緊張してしどろもどろになりながらも質問への受け答えをこなし、一緒に研究してもらうことに漕ぎ着けました」
研究を分かりやすく伝える
子どものころ、家族に名古屋や東京の科学館に連れて行ってもらったことが、科学の面白さに気づくきっかけだった。
そんな機会を子どもたちに経験してもらいたいと、名古屋大学の理系学部の女子学生らで作る「あかりんご隊」という団体に加わり、小学生向けの科学教室を開いたり、科学館での催しで科学実験をしたりしている。
サイエンスコミュニケーションの技術を深めることにも関心があり、イラストの上手い研究室の後輩と、GTRの院生企画の制度を活用してサイエンスイラストレーションに関するセミナーも企画。プロのサイエンスイラストレーターから、研究を分かりやすく伝える技術を学ぶことができた。
GTRでは他にも、博士課程に進学する同期、先輩後輩と交流できる機会を通じて刺激を受けているという。
「定期的に、同世代の頑張っている姿を見られる機会があると、モチベーションが上がります。分野の違う人とたくさん話すことができるので、自分の研究を分かりやすく伝える練習にもなっています」
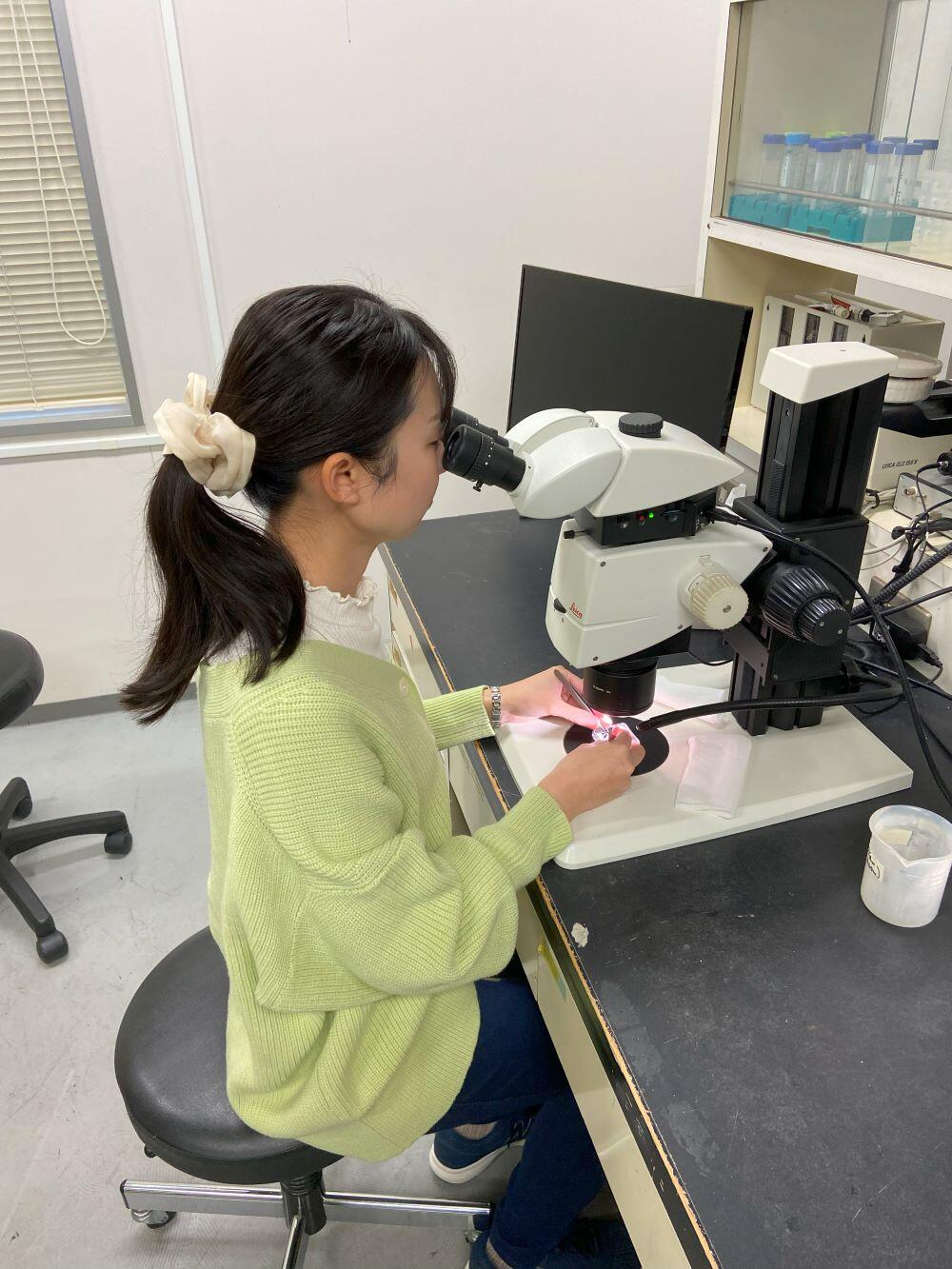
経験ゼロでも、学びながら何とかする
学部1年の講義で、細胞の中をタンパク質が歩く動画を見て、「こんなにいろいろな分子が体の中をダイナミックに動いているんだ」と衝撃を受け、生物に興味を持ったそうだ。
所属する研究室では生き物の行動を神経科学の側面から研究しているが、行動解析、画像解析、細胞のライブイメージング、免疫染色などさまざまな実験技法を駆使する。実験装置を自作することも多いそうだ。
「生物の知識だけでなく電子工作の知識まで必要というのは予想外でした。それまで一回もやったことがなかったハンダ付けもやりましたし、イメージングの装置が壊れたときは自分たちで直しました」
先輩に聞いたり、ネットで調べたりしながら、「まずはやってみよう」と試行錯誤してきた。
また、実験の目的にあわせ、数十種類以上のハエを使いこなす。
「行動を見たり、脳を見たり、いろいろなスケールでものを見るために、それに応じて違ったセットアップを自分でつくらないといけません。自分にとって全く初めてのことを一からやる経験を、たくさんさせてもらえる研究室です」
たとえ経験ゼロでも、やらねばならない目標に向かって何とかする力が身についたという。
「将来、就職して、ハエの研究が直接生かせることは少ないかもしれませんが、何歳になっても新しいことを一から勉強しなければいけないことはあると思うので、研究で培った、ゼロからでもやれる気力や辛抱強さを生かせたらと思います」
(2024年11月インタビュー)

理学研究科 理学専攻(生命理学領域)博士前期課程2年
葉緑体の配置メカニズムを探る
最先端のイメージング技術を駆使して植物を細胞レベルで観る「光生物学グループ」に所属。植物の細胞内小器官の中でも特に、光をエネルギーに変える働きをする葉緑体が、どのようにして細胞内で適切に配置されるのかを研究している。
「教科書などで見かける植物細胞の図では、細胞内小器官が無秩序に配置されているように見えますが、実は、すごく巧妙な仕組みがあります」
植物細胞内にはいろいろな働きをする細胞内小器官が存在しており、その配置は何らかの因子によって適切に制御されているが、メカニズムの多くは詳しく分かっていない。
「動かないイメージがある植物ですが、実は細胞レベルでは緻密な制御のもと様々な『動き』をしています。この動きを実際に見て、仕組みを知りたいと思い、現在の研究室を選びました」

化学の手法を駆使して、未知の因子を探す
GTRの融合研究では、有機化学の研究室と一緒に、「ケミカルバイオロジー」と呼ばれるアプローチで葉緑体の配置を制御する未解明の因子を探索している。「ケミカルバイオロジー」は化学的なアプローチで生命現象を解明する手法で、未知の遺伝子やタンパク質の機能、新たな生理活性物質を特定する際などに有効な研究手法だ。
今回の場合は、葉緑体の配置に特定の変化をもたらす化合物をスクリーニングし、その化合物と結合する因子を同定するという作戦だ。
「先行研究で、葉緑体を細胞膜側に係留する因子の存在については確認されていました。また、葉緑体の配置には、複数の係留因子が関わっていることが示唆されており、係留する因子がなくなると、葉緑体はなぜか核の周りに集ります。こうした疑問から、葉緑体を細胞膜側に係留する因子だけでなく、核の周りに凝集させる因子があるのではないかと考え、現在、この因子をターゲットにしています」
今回の作戦で、化合物には2つの役割が求められる。一つは目的とする未知の因子と結合すること。もう一つは、未知の因子とくっついた状態で回収できることだ。
まず、約2万種類の化合物を植物細胞に加え、葉緑体の配置に対して狙った働きをする化合物を候補として絞り込んだ。葉緑体が核の周りに凝集しなくなる化合物だ。この化合物を因子とともに回収するために、融合研究先のパートナーに、様々な化学修飾を加えた計二十数種類の化合物を作ってもらった。
しかし、修飾後、試してみると、どの化合物も葉緑体に対して狙った働きをする機能を失ってしまっていた。
「変えられる部分を全部変えてもらったのですが、結果は全てダメでした。まるで、進もうとしている目の前に穴があって、その全てに落ちているような感覚でした」
別のアプローチで因子を探す研究も並行して進めていたが、どうしても諦めきれなかった。
「葉緑体に対して狙った働きをする機能はなくなってしまったけれど、もしかすると、目的の因子とくっついている可能性はあるのではと考えました」
その可能性に賭けて実験を続けたところ、作成した化合物が目的とする因子と結合している可能性を示唆する結果が得られた。ターゲットを見つけられる可能性が、まだ残っていることを意味する。
「せっかく作ってもらった化合物をなんとか生かしたいという気持ちがありました。ようやく光が見えて、次のステップに進む目処が立ったところです」
密なコミュニケーションが研究を加速
因子を探すための化合物の合成は、融合研究先の、一学年後輩の学生に担当してもらっている。
お互いの研究室はトランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)にあり、ここでは生物系の研究室と化学系の研究室が同じフロアで研究している。
「化合物ができたらすぐに持ってきてくれて、私もすぐに実験して結果をフィードバックします。『ダメだったよー』『ダメでしたか、それなら』といった具合に、すぐにコミュニケーションが取れて、実験を重ねていけます」
化学の知識で分からないことがあったときも、すぐに聞いて解消ができるそうだ。
「ただ化合物を作って提供してくれるのではなく、向こうからも積極的に提案をくれます。短いスパンで様々な可能性を試せたのは、こちらの研究を理解して、常に前向きな姿勢で協働してくださったおかげです」
ポジティブさ、楽しむことを大切に
日々、物事の中に必ず良い面を見つけるようにしている。「今日は良いことがなかったな」という日でも、後から振り返ると意味があると思えるよう、心がけている。このポジティブな姿勢は母親譲りだという。
実験がうまくいかない日々が続いたときも、「なんとかなる」と手を動かし続けた。
「研究は苦しいときもありますが、サイエンスの本質はワクワク感や楽しさだと思っています」
日々の実験はほとんどがうまくいかないが、時々うまくいって嬉しいこともある。どうしてだろうというワクワクや、明らかになったときの喜びを感じながら、サイエンスを楽しむことを忘れずに研究を続けていきたいと話す。
(2024年11月インタビュー)

理学研究科 理学専攻(生命理学領域)博士前期課程2年
数理科学と生命医科学研究の融合をめざす
生物学や生命医科学の研究分野に数理モデルや機械学習を応用する、異分野融合生物学研究室に所属している。
最近手がけているテーマの一つは、新型コロナウイルス感染症のワクチンに関し数理モデルと機械学習を使って接種戦略の課題解決を目指す研究だ。ワクチンによって誘導される免疫の度合いには個人差があり、この差を推定できれば、最適な接種計画づくりに役立ち、次の変異種や新しい感染症の対策に生かせる。
この研究には、「福島ワクチンコホート」と呼ばれる、福島県在住の約2500人のデータを使っている。新型コロナのワクチンを接種した人に定期的に血液検査をしてもらい、免疫の状態を追跡しているデータだ。
研究参加者に病院に来てもらって採血をするのは手間がかかるので、血液検査のデータは数か月に一度程度のものしかない。そのため、間隔があいたデータをもとに、どんなふうに免疫反応が変化したかを連続的に推定できる数理モデルをつくった。このモデルでは、免疫のすぐつく人、あまり変わらない人、すぐに落ちてしまう人などのタイプ分けができる。
ここからさらに一歩進めて、タイプ分けに機械学習を組み合わせることに取り組んでいる。年齢や体重などから、その人のワクチンに対する反応が、どのタイプなのか推定できるようにしようとしている。
「ワクチンをどんな間隔で接種すればいいのか、どんな人を優先すればいいのかなどが予測できれば、社会全体のワクチン接種のコストを下げられ、感染症対策に役立ちます」

違う視点で世界を見ている共同研究相手の関心を想像する
所属する研究室は、数理モデルとコンピュータシミュレーションを駆使して数理科学の手法から生命医科学を研究している。共同研究が盛んで、医療現場でワクチンを接種する医師、細胞を相手に免疫反応を研究する人たちなど、異分野の専門家と一緒に研究を進めるのが当たり前だという。
そんな環境の中、コロナ禍における高校生の抑うつ状態の変化に関する研究や、臨床治験の参加者を効果的にリクルートする方法に関する研究など、複数の融合研究テーマに取り組み、成果をあげてきた。
心がけているのは、融合研究の相手が、自分とは違う視点で研究対象を見ていることを意識することだという。そして相手が何を知りたいと思っているのか、自分に何を期待しているかを想像する。
「数学的解析を細かく説明することが期待されていない場面で、そこに力点を置いてもうまくコミュニケーションはとれません」
また、いつもアンテナを広げておくことを大切にしているという。人工知能学会、分子生物学会、医療AI等さまざまな学会に出かけて発表やポスターを幅広く眺め、自分の研究に生かせると思ったら、論文を読んでさらに深く理解する。
GTRでも、異分野の学生の研究の様子を聞きながら、「自分の手法を使えばこんな展開ができるかも」と考えたり、逆に相手側から「この研究に、あなたの解析方法を使うことはできませんか」と提案されたりして、世界が広がるのが楽しいと話す。
新しい解析手法で生命現象を解き明かしたい
大学に入るまでは物理や数学に興味があり、生物分野の勉強はほとんどした経験がなかったそうだ。大学で理学部に入り、専攻を選ぶ際に「違うことがしたい」と思い、生物の分野に進んだ。大学の講義で、生命現象の背後にきちんと仕組みがあることを知り、それを解き明かすことに興味を持ったのがきっかけだという。
今は、数学や物理を応用した解析方法と、データ数が限られ再現性を確保するのにも苦労する生命現象とを繋げる異分野融合の組み合わせの妙味を楽しんでいる。
生命科学を読み解く数理科学の解析手法は数多いが、現在、主に用いているのは、エネルギー地形解析という多次元の時系列を解析する方法で、元々は脳波のデータ解析などに利用してされてきたものだ。
「今は他の研究者が作った解析手法を応用して数理モデルに使っていますが、将来は自分で解析手法そのものを生み出し、それで生物の世界を説明できるようにしたい」
(2024年11月インタビュー)

生命農学研究科 応用生命科学専攻 博士後期課程1年
ホタルが光る源の物質を化学合成で作り出す、新たな方法を開発
ホタルが発光する素になる物質「ホタルルシフェリン」の合成に関する研究をしている。
ホタルルシフェリンは、特定の遺伝子の発現量を調べるなどの用途で生物学や医学の実験でも試薬として広く使われている。人工的に化学合成する手法はすでに確立されているが、従来の合成方法は多段階で、コストが高い。
自身は、一つのフラスコで連続的に反応を行い、溶媒や試薬も節約できる新しい方法を開発した。簡単かつ短時間、低コストでホタルルシフェリンを作ることができる方法だ。
もともとは研究室の先輩が、簡単な原料を混ぜてルシフェリンができる反応を偶然見つけ、自身はその研究を引き継いだ。課題だった収率の低さの改善に取り組んだが、なかなか良い方法は見つからなかったそうだ。
ブレイクスルーとなったのは、GTRの中間審査「QE1」で、別の研究室の教員から受けた指摘だった。
「最初に偶然見つかった反応経路に囚われていた自分に対し、『もっと他の経路も考えられるのではないか』とアドバイスをいただいたことで、合成方法を見直し、成功につなげられました」
自分の研究スタイルを大切に
学部生と比較すると、博士課程では同世代の学生とのつながりが薄くなりがちだ。GTRでは、研究室や分野を越えて同世代の学生と繋がりができることが貴重だという。1泊2日のリトリート合宿では、2日間集中してグループワークに取り組み、夜遅くまでプレゼン資料を作ったり議論したりした。そんな活動を通じて、同じように博士課程を志す仲間と仲良くなれた。
また、研究内容や研究スタイルの違いを知る機会にもなったそうだ。
「分野が違うと一回の実験にかかる時間や実験のサイクルが全く異なっていて、それによって研究生活も違って面白いと思いました」
自身は朝型の研究生活を心がけているそうだ。有機合成の実験は時間がかかるので夜遅くまで残ってしまいがちだが、朝の方が頭が冴えて効率的と考えている。
「自分なりのルーティンをつくって、それを毎日続けることを大事にしています」
化学合成の先にある生き物とのつながり
理科に熱心だった小学校の先生がきっかけで、理科が好きになった。生物への関心から大学では農学部を選んだが、大学で受けた有機化学の講義が面白く、有機合成を専門とする研究室に進んだ。
研究テーマを選ぶ際、ネコやフグなど生き物に関わるいくつかの化合物が候補にあったが、「幻想的だ」と感じたホタルを選んだ。
「理学部や工学部にも有機合成化学の研究室はありますが、天然物の合成研究では、合成する物質の先に、自然界でその物質を作っている生き物の存在があります。自分が手を動かして合成しようとしているものを、自然界で生き物が作っている。この自然とのつながりを意識できるところが大きな違いだと思います」
融合研究でホタル体内の生合成を探る
現在は、発光生物の研究者との融合研究で、ホタルの体内で実際にホタルルシフェリンがどのように合成されているかを明らかにしようと研究している。フラスコで溶液を混ぜる有機合成の研究から、ホタルの蛹をすりつぶして体内の物質を探る研究へとアプローチは大きく切り替わった。
ホタル体内の合成経路は、中間物質が不安定で少量と考えられるため検出が難しく、これまで研究が進んでいなかった。自身が開発した新しい反応経路は、ホタルが実際に行っている反応と近いと考えており、そこから予測される中間物質をホタルから見つけ出そうとしている。
生物学からアプローチしてきた人と異なり、有機合成の手法で研究してきた経験から「こういう物質が見つかるのではないか」と仮説を立てられるのが強みだ。
「博士課程の残りの時間で、生合成の経路を行けるところまで明らかにしたい。もしかすると最悪の場合、何も見つからない可能性もあります。でも、そうなったとしても、自分の経験にはなります。大学だからこそできる、知的好奇心に基づいた挑戦的な研究に取り組むことで、得られるものは多いと思います」
(2024年11月インタビュー)

創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 博士後期課程3年
オルガノイドで大脳の仕組みを探る
iPS細胞を用いて、ヒトの大脳の構造や機能を再現した「神経オルガノイド」を作成する研究をしている。オルガノイドは、iPS細胞などの幹細胞で作られた、臓器を模した細胞の塊だ。
本物の人間の臓器を実験に使うことは難しいが、オルガノイドを用いることで、例えばヒトに特有の疾患を実験室内で研究できる。創薬や医療の発展に貢献する、最先端の研究分野だ。
これまで、大脳のオルガノイドは、成熟度合いが未熟なことが欠点となっていたが、より成熟度の高いヒト大脳を模したオルガノイドの作成に成功した。
ヒトの大脳では、大脳皮質と視床という領域が密に情報伝達を行っている。ヒトの大脳と同様に、大脳皮質と視床の2種類の神経オルガノイドを作り、それを組み合わせて相互作用させることで、より高度な機能の再現に成功した。
大脳皮質のオルガノイド単独では、受胎後約9週齢程度の成熟度しか再現されていなかったが、視床オルガノイドとの相互作用により、17週齢相当まで発達した。
「視床から大脳皮質に軸索が延び、その後、大脳皮質からフィードバックが起こる、そういった相互作用の時間パターンまで再現できました」
当たり前のことを確実に丁寧にやる
神経オルガノイドは、安定して作るのがとても難しい。
約1万個のiPS細胞を脳の特定部位の細胞に分化させ、3〜5ミリ程度の大きさの3次元の細胞の塊を作成する。3次元の凝集体であるオルガノイドは、一般的に行われる細胞の2次元培養より、細胞の分化状態にばらつきが生じやすい。
「安定した実験結果を得るためには、オルガノイドの品質を一定にすることが重要です」
ばらつきを抑えるコツは、培養条件を厳密に揃えることだという。例えば、2日に1回行う培地の交換は、同じ時刻に実施するようにしている。また、iPS細胞からオルガノイドを作成するタイミングも、iPS細胞を培養皿に播種してから、決まった日数後の同じ時間に行うなど、タイミングを揃えることを徹底しているという。
「以前は、同じ作業を日によって異なる時間にやっていたこともありました。そうすると、見事に品質がばらついてしまいました。そこが実験の結果にクリティカルに影響していると実感し、そういった失敗を経験しながら、実験手技をコツコツと身につけてきました。当たり前のことを確実に丁寧に実行することが、成果につながると思っています」
GTRのつながりを生かして融合研究先を見つける
融合研究では、京都大学の有機化学の研究室の力を借りた。この研究室が持つ技術にたどり着けたのは、GTRの人のつながりによるものだったそうだ。
神経オルガノイドでシナプスの形成過程を調べる際、従来の免疫染色の方法では難しく、細胞膜上にある受容体だけを標識する化合物を探していたところ、同じ名古屋大学の研究室に手がかりがありそうだという情報を得た。
その研究室はGTRの同期が所属する研究室で、連絡を取ったその日のうちに「じゃあ今日この時間にディスカッションしよう」と返答があり、すぐに話を進めることができた。
そして、その分野に強い京都大学の研究者にコンタクトを取った方が良いとアドバイスをもらい、融合研究につながった。
「GTRでは、イベントなどを通じて学年や所属を越えてつながりができます。他のラボの方とも簡単にコミュニケーションが取れ、融合研究を推し進めるのに適した環境です」
人を巻き込み、研究を進める楽しさ
研究に興味を持ったのは小学生のころ。アニメに登場する博士のイメージに憧れ、宿題をするのも「ちょっと部屋にこもって研究する」と親に言っていたそうだ。当時は研究を「一人で黙々と進めるもの」と考えていたが、今は、「どんな研究も一人では絶対にできない」と感じているという。
人を巻き込み、いろいろな分野の人とディスカッションして研究を進めていく過程が「一番楽しい」と話す。自分のプロジェクトにいろいろな人を巻き込むことができるのが、自身の強みだと自己分析している。
「協力していただく際は、知恵をもらうだけでなく、自分からも積極的に提供する姿勢を忘れないようにしています。また、結果が出るまで全力で取り組むよう心がけています」
博士課程修了後は、製薬会社への就職が決まっている。
「いろいろな人とディスカッションしながら研究を発展させる、その過程が楽しいので、この先どんなテーマであっても、研究を楽しんでいけると思います」
(2024年11月インタビュー)
