GTR学生ワークショップ2020を開催しました。
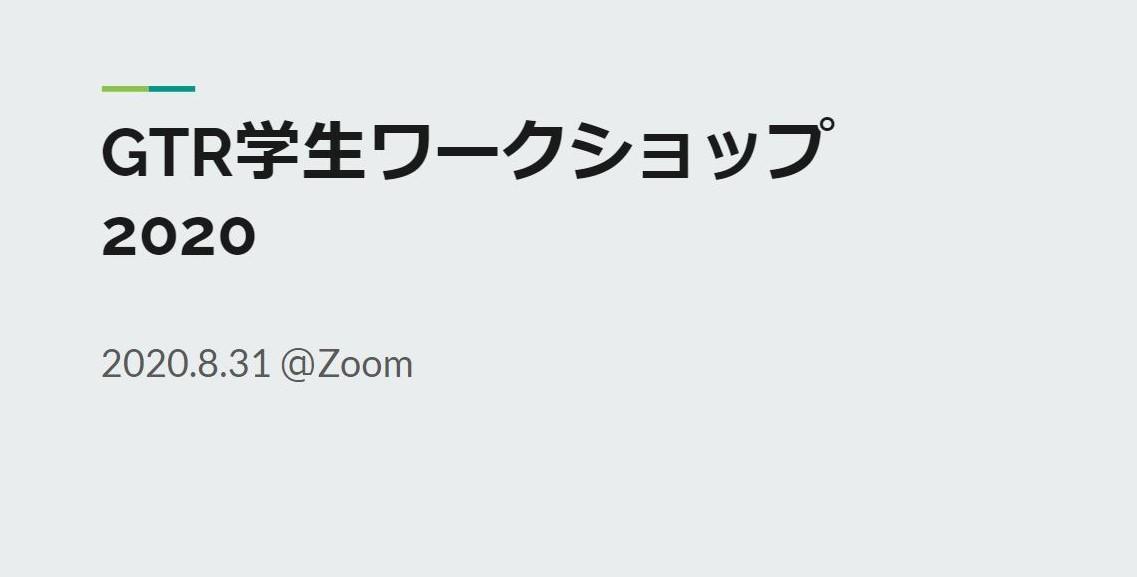
8月31日(月)、プログラムのマインドや学生同士の意識を共有し、GTRで異分野融合に取り組む意義について考える「GTR学生ワークショップ2020」を開催しました。
当日は、GTR生のほぼ全員が参加し、パネルディスカッションやグループワークを行いました。
【イベントプログラム】
- 山口先生からの導入
- グループワーク1:自己紹介
- パネルディスカッション
- グループワーク2:「融合をつくりだす」について考える
- 共有・振り返り
山口先生からの「融合をつくりだす」というテーマについての導入
はじめに山口先生から、融合研究への取り組みを通じて「研究突破力」を養成する意義についての導入がありました。
異分野融合は、組織のカタチだけをつくっても成せるものではなく、「融合をつくりだす人」の存在が重要です。GTRが目指す「研究突破力」とはまさに、「融合をつくりだすことができる力」と言えます。
融合について考えるパネルディスカッション
パネルディスカッションでは、7名の先生方に、ご自身の経験や融合研究に関する様々な「問い」にお答えいただきながら、GTRの目指す「融合研究」の本質や、「融合をつくりだす」ことの意味や意義について考えました。
「融合をつくりだす」について考えるグループワーク
グループワークでは、「融合をつくりだす」というテーマについて、以下の4つの切り口からブレインストーミングを行いました。
- 動機・モチベーション
- 融合の魅力・価値とは?融合が必要な理由は?融合はどこで必要とされているのか?
- 自分にとって
- 自分のキャリアにとっての「融合をつくりだす」ことの意味?
- 未来・世界
- 「融合をつくる」ことができたら、未来・世界にどんな価値を提供できる?「融合をつくる」ことで、科学技術の舞台で世界とどう競う?
- 難しさ・必要な力
- 融合の難しさとは?乗り越えるには?必要な力?
各々が、「融合をつくりだす」について4つの切り口から考え、さらにグループの他のメンバーとのディスカッションを通じて、考えを深めました。
最終的に、自分たちにとってしっくりくる言葉で「融合をつくるとは?」を表現することをグループワークのアウトプットとし、グループで話し合ったことをキャッチコピーという形に集約しました。
最後に全体で各グループのキャッチコピーを共有し、投票を行いました。投票で上位だったキャッチコピーを以下にご紹介します。
無知から未知へ 未知から英知へ
価値の次元を拡張する
常識を知って、常識を超えていけ
0から1より、1+1
今回のイベントでは、「融合をつくりだす」というテーマについて他者と一緒に考えることを通じて、様々な価値観や考え方が相互作用し、スタート時とは違うものの見方や新しい気付きを得て、GTRで活動することの意味や意義を自分事化すること、「融合研究」に対する理解を深めることを目指しました。
以下に、イベント終了時にZoomのチャットに書き込んで頂いた参加者の「気づき」から、一部をご紹介します。
- 複数人で考える大切さを再認識しました
- 自分1人で考えていては出なかったような意見が出た
- 会話する機会が研究をする上でも大切なことだと気付いた
- 融合研究の意義を再考できて良い機会でした
- 他の博士学生の考えを知ることで、自分と違うことや同じことがわかって、これも一つの融合だなあと思いました
- 融合研究について新しい視点を持てた
- 人それぞれ多様な観点で融合研究を捉えていることが実感できた
- ブレインストーミングで他の人が考えている過程まで見られて新鮮だった
- 研究力に加えて人間的にも成長できる
- 自分の研究にばかり囚われていることを痛感した
- コロナ禍で研究室に行って議論することができない中、議論して他人の考えを聞き、そこから価値観を広げることの重要さを感じました
- 意見を一つにまとめることの難しさを感じました
- 一人ではちっぽけな考えでも、仲間と話し合うことで(かけ合わさることで)、高次元に飛躍した!!
- 融合研究の先に見据えている目的を他の人とシェアできて非常に勉強になりました。自身の考え方にも是非取り入れたいと思います
- 融合とは何かという意見だけでも自分にはない目からうろこの様な発見がいくつかあった、異分野の人から自分のテーマを見たらきっともっとたくさんの新たな発見があるのだろうと思う。自分の枠にとらわれず、新たな挑戦をしていきたい
